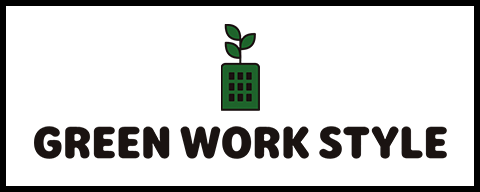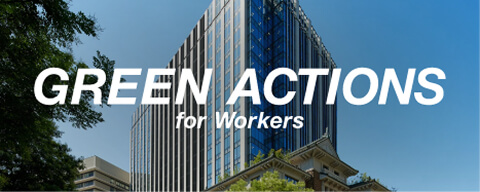【WEBいきもの図鑑】01|シジュウカラ

こんにちは。「Midori_Times.net」編集部です。
広域渋谷圏に暮らすいきものたちをご紹介する本シリーズ。第1回目の今回は「シジュウカラ」です。シジュウカラは古くから私たち日本人に親しまれてきた身近な野鳥の1種。森や里山、都市の公園などに広く生息し、バードウォッチングの対象としても人気があります。
実は、シジュウカラは生物多様性における指標種(※)に位置付けられていて、私たちが環境やいきものたちの変化を捉えるうえで大切な役割を担っています。具体的な生態や人との関わりについて見ていきましょう。
※その分布状況などを調査することにより、特定の環境の状態を推測・評価できる生物
シジュウカラはどんな鳥?
シジュウカラ(スズメ目シジュウカラ科)は、沖縄の一部や小笠原諸島を除く日本全国に生息する野鳥です。森林や里山では樹木の洞、市街地では郵便受けなどの人工物に巣をつくることもあり、春から夏にかけては昆虫、秋は植物の実や種を食べて暮らしています。
体長はスズメとほぼ同じ14cm〜15cm前後。可愛らしい白い頬と、胸から腹にかけてのネクタイのような黒い模様が特徴です。鳴き声には「ツツピー」、「ジュクジュク」、「ジャージャー」などたくさんのバリエーションがあり、それらを組み合わせることで仲間に警戒を呼びかけたり、コミュニケーションをとったりしていると言われています。
ちなみにシジュウカラという名前については、独特の鳴き声に由来するという説のほか、群れている姿がスズメ40羽に見えるためと言われることも。その他にもさまざまな説があるようです。
生物多様性の指標種として

続いて、シジュウカラが自然環境や生態系のなかでどんな役割を果たしているのか見ていきましょう。
繁殖期のシジュウカラは、毛虫や甲虫を大量に捕食します。それによって虫の数が増えすぎるのが抑えられるとともに、時には自身がタカやトビなどの猛禽類の餌になることで、結果的に食物連鎖におけるエネルギー移動の流れを支えています。
また、シジュウカラは森林や里山、都市部など幅広いエリアに生息する一方、環境の変化にとても敏感です。田畑で使われる農薬の量が増えたり、都市部の緑地が減ったりすると、個体数が減少してしまうことから、生物多様性における指標種に位置付けられています。
簡単に言えば、一定数以上のシジュウカラが生息し、繁殖を続けている環境は、人やその他のいきものにとっても暮らしやすい、健全な環境というわけです。
表参道をシジュウカラの棲み家に

こうした観点をふまえ、東急不動産は生物多様性の保全活動の一環として、広域渋谷圏のビルや商業施設にシジュウカラの巣箱を設置する取り組みを続けてきました。
2024年2月27日には、東急プラザ表参道原宿の屋上「おもはらの森」に9棟の「シジュウカラの邸宅」を設置。ワンルームタイプ、楕円ワンルームタイプ、メゾネットタイプという3種類を用意し、シジュウカラの生態にあわせて木材にこだわり抜き、巣穴のサイズも1mm単位で細かく調整しました。
その結果、設置から約1ヶ月半後の4月4日には、スギの木材を使ったワンルームタイプにシジュウカラのカップルが営巣しているのを確認。それから約2ヶ月にわたって親鳥が餌を与えながら雛を育て、5月24日には雛が巣立っているのを見ることができました。
人もいきものも快適に暮らせるサステナブルな街づくりに向けて、東急不動産は引き続き生物多様性の保全に取り組んでいきます。